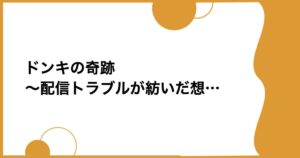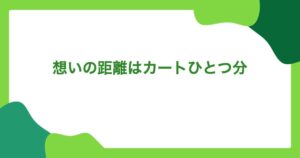雪降る日のゆず茶 ~フリマが繋いだ優しい想い~
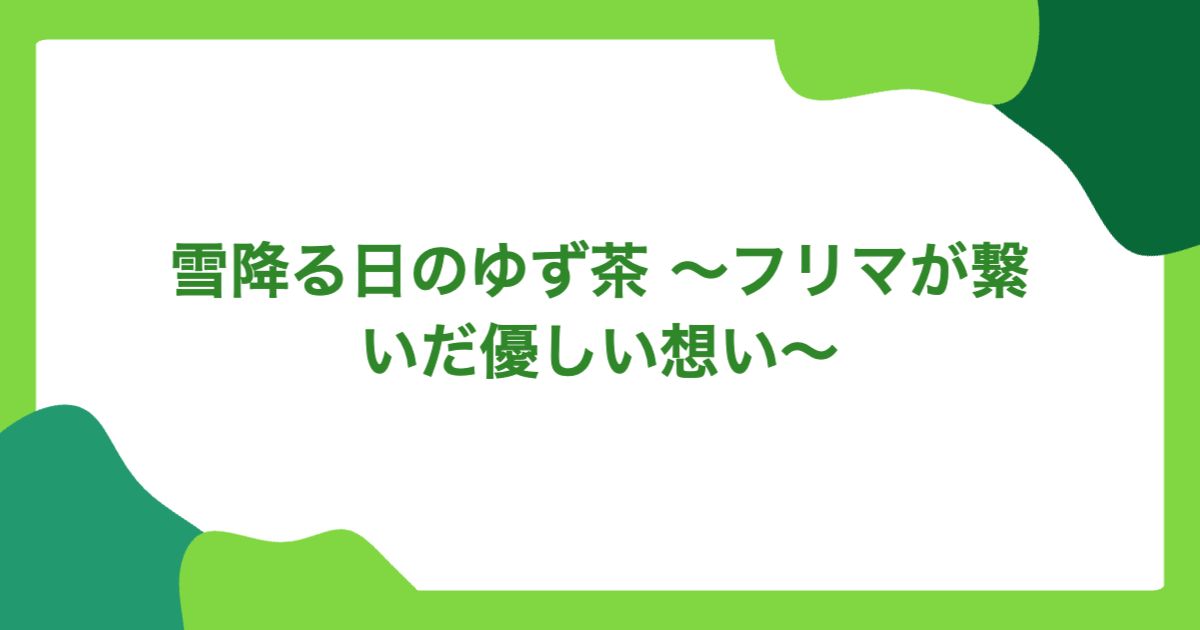
プロローグ
都内某所の公園。週末になると、この場所は地域の人々が集うフリーマーケット会場へと変わる。
不用品に新しい命を吹き込む場所。
出会いと別れが交差する場所。
そして——
二人の運命が動き出す場所。
第一章:予想外の出会い
「えーっと……これは、一体何を売ろうとしているんでしょうか?」
土曜日の朝9時。会場に設置された受付テントで、みずなは目の前の出店申込書を見て困惑していた。
そこには、こう書かれていた。
『出品物:私の人生経験(30年分)』
「え、えーとこれって……?」
みずなは思わず声を出した。人生経験?それって、どうやって売るんだろう。というか、売れるものなの?
「どうかしましたか?」
隣から声がかかった。振り返ると同じく受付を担当していたゆうなが話しかけた。
「あ、すみません。この申込書、ちょっと変わってて……」
みずなが申込書を見せると、ゆうなは少し首をかしげてから、冷静に分析を始めた。
「人生経験……確かに珍しいですね」
ゆうながパソコンで出店の規約を確認する。その手つきは慣れたものですごく頼りがいを感じる。
「でも、規約には『不用品に限る』とは書いてありますが、『物品に限る』とは書いてないんですよね」
「あ、本当だ……」
みずなも画面を覗き込む。ゆうなの冷静な分析力に、少し感心していた。
(この人、すごく落ち着いてる……)
「あの、すみません……」
と、申込者の男性が近づいてきた。60代くらいの、妙に哲学者っぽい雰囲気の男性だ。白髪交じりの髪を後ろで結び、丸眼鏡をかけている。少しくたびれた雰囲気もあったが何か強い思いがあるのが伝わってくる。
「私の人生経験を若い人たちに伝えたくて。フリーマーケットなら、気軽に立ち寄ってもらえるかなと思いまして」
「なるほど……」ゆうなが真剣に聞いている。「つまり、相談コーナーのようなものですか?」
「そうです!人生相談、一回500円なら気楽に来てくれそうで」
「……それ、フリマじゃなくて営業では?」
みずなが小声でツッコむ。
しかし、ゆうなは少し考えてからこう提案した。
「分かりました。では、『人生相談コーナー』という名目ではなく、『昭和の思い出グッズ販売+おまけトーク付き』という形にしてもらえませんか?実際に何か小物を置いて、それを買った方に人生相談をおまけで付ける、という」
「おお!それはいいアイデアだ!」
哲学者風男性は満足そうに頷いた。
(すごい……こんな難しい状況を、一瞬で解決しちゃった)
みずなはゆうなの機転の良さに感動していた。職業柄彼女は規則やルールには敏感だったが、杓子定規になってしまいこうした柔軟な発想は苦手だった。
「ゆうなさん、さすがです!」
「いえ、ルールの範囲内で、みんなが納得できる方法を探しただけですよ」
ゆうなが照れくさそうに笑う。その笑顔は優しくて、どこか安心感があった。
しかし、トラブルはまだ終わらなかった。
「すみませーん!」
次に現れたのは、30代くらいの女性。両手いっぱいに段ボール箱を抱えている。メイクは少し濃いめで、どこか疲れた表情をしていた。
「出店したいんですけど!」
「はい、どうぞ。出品物は何ですか?」みずながペンを構える。
「元カレからもらったプレゼント全部です!」
女性が段ボールを受付テーブルにドンと置く。中から、大量のぬいぐるみ、アクセサリー、手紙の束が見える。
「全部で200点くらいあります!一つ100円でどうですか!」
「に、200点……」みずなが絶句する。
「あの、スペースは一区画3メートル×3メートルなんですが……」ゆうなが規約書を見せる。
「大丈夫です!積み上げます!ピラミッド型に!」
「ピラミッド!?」
みずなとゆうなは顔を見合わせた。
「あの、安全面を考えると、ピラミッド型は少し……」ゆうなが丁寧に説明しようとした、その時——
ドサササササッ!
段ボールの底が抜けて、中身が地面に散乱した。
「きゃああああ!」
ぬいぐるみが転がり、アクセサリーが飛び散り、手紙が風に舞う。ピンクや白の便箋が、まるで桜吹雪のように公園中を飛んでいく。
「あ、あの手紙!大切なラブレター!」
女性が慌てて追いかける。しかし、風はさらに強くなり、手紙は公園の木々の間を縫うように舞い始めた。
「まずい……」
ゆうなとみずなは顔を見合わせた。
「急いで回収だ!」
「はい!」
二人は散乱した手紙を追いかけ始めた。
みずなは必死で走る。運動は得意ではないが、今は必死だった。木に引っかかった手紙を背伸びして取り、ベンチの下に飛んでいった手紙を拾い、池に落ちそうな手紙を間一髪でキャッチ。
ゆうなも同じく、公園中を走り回っている。ラブレターを他の人に見られたくない気持ち分かるし、誰かに見られる前にとにかく木の枝に引っかかった手紙を取り、遊具の隙間に入り込んだ手紙を回収していく。
「みずな、そっちは大丈夫!」
「はい!こっちは何とか!」
二人の息はぴったりだった。言葉を交わさなくても、お互いがどう動くべきか分かる。お互いを理解してるから、細かく言わなくても体が勝手に動くから自然に協力できている。
15分後、汗だくになった二人は、なんとか全ての手紙を回収した。
「はぁ……はぁ……全部、回収できましたか?」みずなが息を切らしながら聞く。
「はい……多分……」ゆうなも同じく息切れしている。
二人は疲れ果てて、受付テントの近くのベンチに座り込んだ。
「フリマ運営って……こんなに大変なんですね」みずなが額の汗を拭う。
「そんなことないと思うけど……想像以上だね」ゆうなも水筒から水を飲む。
二人は少しの間、無言で空を見上げた。秋晴れの青空が、どこまでも広がっている。
「でも……」みずなが小さく呟く。「ゆうなさんと一緒で、良かったです」
「え?」
「一人だったら、絶対パニックになってました。ゆうなさんが冷静に指示してくれたから、なんとかなりました」
「いえ、みずなが一生懸命走ってくれたおかげだよ」
ゆうなが優しく微笑む。その笑顔を見て、みずなの胸が少し温かくなった。
しかし、その時。
「ありがとうございました!」
元カレグッズ女性が、涙目で感謝してきた。
「お二人のおかげで、大切な……いや、もう大切じゃないけど、でも思い出の手紙が無事でした!」
「いえ、良かったです」ゆうなが優しく微笑む。
「あの、お二人って付き合ってるんですか?息ピッタリですね」
「え?」
「いえ、そういうわけでは……」
みずなが慌てて否定する。顔が真っ赤になっている。
「そうですか?でも、なんかお似合いですよ」
女性がニヤリと笑って去っていく。
みずなは顔を伏せたまま、小さく呟いた。
「……お似合い、か」
(ゆうなさんみたいな人と……いや、違う違う。ゆうなさんは尊敬する先輩みたいな存在で……ただ、冷静で、優しくて、かっこいいだけで……)
みずなの心は、少しざわついていた。
そして、フリーマーケット本番が始まった。
「では、開会します!」
ゆうなの掛け声で、地域フリーマーケットがスタート。来場者がぞろぞろと集まり始める。
哲学者風男性のブースには、意外にも若い人たちが集まっていた。「昭和の思い出グッズ」の中から、古いカメラやレコードを手に取りながら、人生相談を受けている。
「最近、仕事で悩んでて……」
「焦らなくていいんだよ。人生は長いんだから」
温かい会話が、そこにはあった。
元カレグッズ女性のブースも、予想外に人気だった。「この手紙、内容が気になる」という野次馬心で集まった人々が、結局は商品を購入していく。
「このぬいぐるみ、可愛いですね」
「ありがとうございます!元カレ、センスだけは良かったんですよね」
女性の吹っ切れた笑顔が、清々しかった。
「なんだか、うまくいってますね」みずなが嬉しそうに言う。
「そうですね。良かったです」
ゆうなも満足そうに頷く。
しかし——
「あのー、すみません」
またスタッフが困った顔で近づいてきた。
「この出店者さん、ずっと寝てるんですけど……」
スタッフが指差す先には、椅子に座ったまま爆睡している中年男性が。目の前には「激安!なんでも100円!」という看板と、大量のガラクタが並んでいる。よく見ると、口を開けて盛大にいびきをかいている。
「起こしても起きないんです」
「えっと……」
みずなとゆうなは顔を見合わせた。
こうして、予想外のトラブル続きで始まった地域フリーマーケット運営。
二人の長い一日は、まだ始まったばかりだった。
第二章:協力が深める絆
フリーマーケット運営が始まって、一ヶ月が経った。
毎週土曜日、ゆうなとみずなは朝8時に公園に集合し、受付準備を始める。最初は緊張していた二人も、今では自然に役割分担ができるようになっていた。
ゆうなは機材のセットアップと出店者への説明を担当。みずなは書類整理と来場者の案内を担当。二人の連携は、回を重ねるごとにスムーズになっていった。
そして、今日もまた、新たなトラブルが待っていた。
値札事件
「みずな、これ……」
ゆうなが、みずなの作成した値札シールを見て、静かに呼びかけた。
「はい?どうかしましたか?」
みずなが顔を上げる。
「この値札、数字が……逆になってない?」
ゆうなが指差したのは、「600円」と書かれるべきところが「900円」になっているシール。そして「9,000円」と書かれるべきところが「6,000円」になっているシール。
「え……?」
みずなが自分の作成した値札を確認すると、顔が真っ青になった。
「6」と「9」を、あるあるの間違いだが・・・・・・・
「ど、どうしよう……もう出店者さんに渡しちゃいました……」
みずなの声が震える。几帳面な性格の彼女にとって、こうしたミスは致命的なものに感じられた。
「落ち着いて」ゆうなが優しく言う。「今から一緒に回って、全部貼り直そう」
「でも……ゆうなさんの時間を使わせちゃって……」
「大丈夫。僕も昔、似たようなミスをしたことがあるので。まだ間に合うから大丈夫だよ」
ゆうなが微笑む。その笑顔には、責める気持ちなど微塵もなかった。
二人は出店者全員を回って事情を説明し、値札を貼り直して回った。30店舗以上。一時間以上かかった。
最後の出店者——骨董品を売るおじいさんが、笑いながら言った。
「あなたたち、夫婦みたいだね。息がぴったりだ」
「え?」みずなが真っ赤になる。
「いやいや、僕たちはただの……」ゆうなも慌てる。
「ははは、照れなくていいよ。いいコンビだ、本当に」
おじいさんは、温かい目で二人を見ていた。
作業が終わり、二人はベンチで休憩した。
「ゆうなさん……本当にすみませんでした」みずなが頭を下げる。
「いえ、大丈夫だよ」ゆうなが笑う。「むしろ、みずながいつも丁寧に仕事してくれるから、僕も助かってるし」
「そんな……私なんて、失敗ばかりで……」
「そんなことないって」ゆうなが真剣な顔で言う。「みずなは、とても几帳面で、気配りができて、出店者さんたちからも信頼されてるし」
「……本当ですか?」
「本当だよ。今日も頑張っていこう」
ゆうなの言葉は、嘘がなかった。みずなは少しだけ、胸が温かくなった。
(ゆうなさん……本当に優しい人だな)
出店者対決
二週間後、新たな事件が発生した。
「そっちがはみ出してる!」
「いや、そっちだ!」
隣同士に配置された二人の出店者——骨董品を売るおじさんと、手作り雑貨を売るおばさんが、場所取りで大喧嘩していた。
「この線、見えないの!?」
「見えてるわよ!でも、あなたの荷物がこっちに来てるじゃない!」
二人とも譲らない。周りの出店者たちも困惑している。
「どうしましょう……」みずなが困り果てていると、ゆうなが冷静にメジャーを取り出した。
「測ってみましょう。正確に」
ゆうなは慎重に、両方のブースの寸法を測った。そして、結果を告げる。
「お二人とも、規定内に収まってます」
「え?」
「じゃあ、何が問題なの?」
二人の出店者は、同時にゆうなを見た。
「多分、お互いの荷物の配置が原因です」ゆうなが図を描きながら説明する。「骨董品は平面的に並べる必要があって、手作り雑貨は立体的に展示したい。だから、お互いの『理想の配置』が衝突してるんです」
「なるほど……」
二人の出店者は、少し納得した顔をした。
「では、こうしてみてはどうですか」ゆうなが提案する。「お二人の商品を、コラボさせてみては?骨董品に手作りの布を添えるとか、古いカメラに手作りのストラップを付けるとか」
「おお!」
「それ、面白いかも!」
二人の出店者は、突然目を輝かせた。
「昭和レトロと現代ハンドメイドのコラボか……」
「新しいジャンルができそうね」
二人は意気投合し、その場でコラボ商品を作り始めた。
みずなは、その様子を見て感動していた。
「ゆうなさん、すごい……発想が天才的です」
「いえ、たまたまですよ」ゆうなが照れる。「IT業界にいると、対立する要件をどう統合するか、っていう思考が癖になってて」
「そういうものなんですね」
みずなは、ゆうなの横顔を見つめた。冷静で、優しくて、頭の回転が速い。そして、誰に対しても思いやりを持って接する。
(かっこいいな……)
みずなの心の中で、「尊敬」という感情が、少しずつ別の何かに変わり始めていた。
迷走する外国人
さらに二週間後。
「ハロー!アイ、ウォント、セル!」
受付テントに、日本語がほとんど話せない外国人がやってきた。30代くらいの男性で、金髪に青い目。どこの国の人かも分からない。
「あ、はい……出店申込ですね?」みずなが申込書を渡す。
しかし、外国人は申込書を見て困惑した顔をした。どうやら、日本語が読めないらしい。
「えっと……イングリッシュ?」みずなが聞く。
「ノー、ノー」外国人が首を振る。
「……フレンチ?」
「ノー」
「スパニッシュ?」
「ノー」
完全に行き詰まった。
外国人は、必死に身振り手振りで何かを伝えようとする。手を広げて、何かを掴む仕草。次に、手を振る仕草。そして、ニコニコ笑う。
「えっと……これは……魚?いや、鳥?」みずなが必死に解読を試みる。
「違う気がするなぁ……」ゆうなも首をかしげる。
「ちょっと待ってください」
ゆうながスマホの翻訳アプリを起動した。しかし、相手の国の言語が分からない。
「とりあえず、出品物を見せてもらいましょう」
ゆうなが身振りで伝えると、外国人は嬉しそうに頷いた。持ってきた段ボールを開けると——
中には、大量の「招き猫」が入っていた。
「ああ!日本のお土産を売りたいんですね!」みずなが叫ぶ。
「イエス、イエス!」外国人が嬉しそうに頷く。
ゆうなは、翻訳アプリで「日本の伝統工芸品」と入力し、複数の言語で表示させた。すると、外国人が画面を指差した。
「ポーリッシュ!」
「ポーランド語ですか」ゆうなが言語を切り替える。
なんとか意思疎通に成功し、無事に出店許可が下りた。
当日、そのポーランド人のブースは、外国人観光客で大賑わいになった。招き猫を買った観光客たちが嬉しそうに写真を撮っている。
「ゆうなさんの機転、本当にすごいです」みずなが感心して言う。「私だけだったら絶対パニックになってました」
「いえ、みずなが粘り強くジェスチャーで対応してくれたおかげですよ」ゆうなが笑う。「二人だから、なんとかなったんです」
みずなは、その言葉が嬉しかった。
「二人だから……」 そう、二人だから。一人じゃできなかったことが、ゆうなと一緒ならできる。
第三章:観察力と優しさ
フリーマーケット運営が始まって、三ヶ月目。
秋も深まり、公園の木々が色づき始めた頃。今日も、多くの出店者と来場者で賑わっている。
「みずな、おつかれさま」
ゆうなが差し出したのは、温かいお茶のペットボトル。
「ありがとうございます」
みずなが受け取る。ゆうなは、いつもこうして気を配ってくれる。疲れている時は休憩を勧めてくれるし、困っている時はすぐに助けてくれる。
(本当に、優しい人だな……)
みずなは、ゆうなと過ごす時間が、どんどん好きになっていった。
しかし、その平和な午後に、事件は起きた。
フリマ泥棒
「商品が盗まれた!」
突然の叫び声に、会場が騒然とした。
駆けつけると、アクセサリーを販売している女性出店者が、真っ青な顔をしていた。
「高価な腕時計が……消えてるんです!」
「いつ、気づきましたか?」ゆうなが冷静に聞く。
「さっきまで確かにあったんです。でも、ちょっと目を離した隙に……」
女性は泣きそうな顔をしている。その腕時計は、亡くなった夫の形見だったという。
「警察を呼びましょう」みずなが携帯を取り出そうとすると、ゆうなが静かに制した。
「ちょっと待ってください。まず、状況を整理しましょう」
ゆうなは出店者に質問し始めた。
「腕時計を最後に見たのは、何時頃ですか?」
「30分前くらいです」
「その時、周りに誰かいましたか?」
「えっと……確か、中年の女性が何人か……」
「その女性たちの特徴は?」
ゆうなは次々と質問していく。みずなは、その様子を見ながら几帳面にメモを取った。
ゆうなは会場の配置図を頭の中で思い浮かべ、目撃情報を整理し、人の流れを分析していく。
そして、静かに言った。
「犯人は……多分、あの人です」
ゆうなが指差したのは、会場の端でウロウロしている中年女性だった。一見、無害そうな主婦風の女性。しかし——
「なぜ、分かるんですか?」みずなが驚く。
「彼女、さっきから同じ場所を何度もウロウロしてるんです」ゆうなが静かに説明する。「普通の来場者なら、興味のあるブースに立ち寄るはず。でも、彼女はどこにも立ち寄らず、ただウロウロしてる」
「それに……」ゆうなが続ける。「バッグの形が不自然に膨らんでます。そして、時々バッグを確認する仕草をしてる。何か隠してる証拠です」
みずなは、ゆうなの鋭い観察力に驚いていた。
二人は、その女性に近づいた。
「すみません、ちょっとよろしいですか?」
ゆうなが声をかけると、女性は明らかに動揺した。
「な、何ですか?」
「実は、盗難事件がありまして。もしよろしければ、バッグの中を見せていただけませんか?」
「そんな!失礼な!私を疑ってるんですか!?」
女性が大声を上げる。しかし、ゆうなは冷静だった。
「疑ってるわけではありません。ただ、確認のためです。他の来場者の方にも協力をお願いしていますので」
「……」
女性は、しばらく黙っていた。そして、観念したように、バッグを開けた。
中から、盗まれた腕時計が現れた。
「あった!」出店者の女性が駆け寄ってくる。
「すみません……つい、魔が差して……」
中年女性は、その場で泣き崩れた。
腕時計は無事に持ち主の元へ戻り、出店者の女性は涙を流して喜んだ。
「本当にありがとうございました!お二人のおかげです!」
「いえ、無事で良かったです」ゆうなが微笑む。
事件が解決し、二人はベンチで休憩した。
「ゆうなさん……すごかったです」みずなが目を輝かせて言う。「どうして、あんなに観察力が鋭いんですか?」
「職業柄、データの異常を見つける癖がつくんです」ゆうなが照れながら答える。「システムの中で、普通じゃない動きをしてるものを見つけるのと、似てるんですよ」
「そうなんですね……」
みずなは、改めてゆうなを見つめた。
冷静で、観察力が鋭い。でも決して人を傷つけず、いつも優しく接する。そして、困っている人を放っておけない。
(本当に……かっこいい)
みずなの心の中で、「尊敬」はもう「恋心」に変わっていた。
でも、それを伝える勇気は、まだなかった。
第四章:段ボールと変化
フリーマーケット運営が始まって、四ヶ月目。
季節は晩秋に差し掛かり、朝晩の冷え込みが厳しくなってきた。
今日は、次回のフリマに向けて、倉庫で出店者用の段ボールを整理する日だった。公園の片隅にある小さな倉庫。そこに、大量の段ボールが積まれている。
「みずな、無理しないでね」
ゆうなが心配そうに声をかける。
「大丈夫です。これくらい」
みずなは、段ボールを一つ持ち上げた。思ったより重い。でも、ゆうなに頼ってばかりいられない。自分も、しっかり働きたい。
「よいしょ……よいしょ……」
みずなは、段ボールを積み上げていく。一つ、二つ、三つ……
しかし、七つ目を積み上げようとした時——
ガシャーン!
バランスを崩して、段ボールタワーが崩壊した。みずなも一緒に倒れ込む。
「きゃああああ!」
「みずな!」
ゆうなが急いで駆け寄ると、みずなは段ボールに埋もれて顔だけ出している状態だった。
「大丈夫!?怪我は!?」
ゆうなが慌てて段ボールをどけていく。
「す、すみません……私、不器用で……」
みずなは、段ボールの下から顔を出して、涙目になっていた。痛いわけじゃない。でも、情けなくて、悔しくて。
「せっかく積んだのに……ゆうなさんの時間を無駄にしちゃって……」
「そんなことないよ」
ゆうなが優しく笑う。その笑顔には、少しも責める気持ちがなかった。
「怪我はないですか?」
「はい……恥ずかしいだけです……」
「良かった」ゆうながホッとした表情を見せる。「また一緒に積み直しましょう。今度は僕が下で支えるから、みずなは上に乗せるだけで大丈夫です」
「でも……」
「一人でやろうとしなくていいんだよ」ゆうなが真剣な顔で言う。「二人でやるから、うまくいくからね」
みずなは、その言葉にハッとした。
そうだ。一人で頑張る必要はない。ゆうなは、いつも一緒にいてくれる。
「……ありがとう」
みずなは、小さく微笑んだ。
二人で協力して、今度は無事に段ボールを積み上げた。ゆうなが下で支え、みずなが上に乗せていく。完璧な連携だった。
「できました!」
「おつかれさま。うん、がんばったね」
二人は、完成した段ボールタワーを眺めて満足げに頷いた。
その時、崩れた段ボールの隙間から、一枚の古い写真が見つかった。
「これ……何でしょう?」
みずなが拾い上げると、そこには古いフリーマーケットの写真が写っていた。20年以上前の写真だろうか。セピア色に色褪せている。
写真の中には、笑顔で手を繋ぐ若いカップルが写っていた。二人とも、とても幸せそうだ。
「昔のフリマの写真かな?」ゆうなが覗き込む。
「みたいですね……」
みずなは、写真の中のカップルを見つめた。こんな風に、自然に手を繋げるなんて、羨ましい。
「いつか、私も……」
みずなが小さく呟いたが、その声はゆうなには届かなかった。
作業を終えて、二人は倉庫を出た。外はもう夕暮れ。オレンジ色の空が、どこまでも広がっている。
「みずな、今日もお疲れ様でした」
「ゆうなさんも、ありがとうございました」
二人は、公園の出口で立ち止まった。いつもなら、ここで別れる。
でも、今日は少しだけ、別れたくない気持ちがあった。
「あの……」みずなが勇気を出して言う。「もしよかったらガストでお茶でも……」
「あ、すみません」ゆうなが申し訳なさそうに言う。「今日、この後ちょっと用事があって……」
「あ、そうですか。すみません、急に言って」
みずなは、少しだけ残念そうに笑った。
「また、今度おれからも誘うね」ゆうなが優しく微笑む。「みずなと紅茶飲むの、楽しみにしてるから」
「……はい」
みずなは、顔を赤らめながら頷いた。
二人は、それぞれの方向へと歩いていく。
みずなは、何度も振り返った。ゆうなの背中が、遠くなっていく。
(ゆうなさん……好きだな)
みずなは、ようやく自分の気持ちに気づいた。
これは、尊敬だけじゃない。
もっと、特別な感情。 でも、この気持ちを伝える勇気は、まだなかった。
第五章:最終日、雪の奇跡
フリーマーケット運営が始まって、半年が経った。
今日は、今シーズン最後のフリマ。12月の寒い朝だった。
「今日で最後ですね」みずなが少し寂しそうに言う。
「そうだね」ゆうなも同じ表情をしていた。「でも、素敵な半年間でした」
二人は、いつものように受付テントを設営する。慣れた手つきで、テーブルを並べ、椅子を置き、看板を立てる。
半年前、フリーマーケット運営のお仕事を始めた時のことを思い出す。手紙が散乱して、二人で必死に走り回ったこと。値札を間違えて、一緒に貼り直したこと。泥棒を見つけて、商品が出店者に戻せたこと。
全てが、大切な思い出だった。
「では、開会します!」
ゆうなの掛け声で、最後のフリマがスタートした。
いつもの出店者たちが、笑顔で挨拶してくる。哲学者風のおじさん、元カレグッズのおばさん、骨董品のおじいさん、手作り雑貨のおばあさん、ポーランド人の青年……
みんな、この半年間で顔馴染みになった。
「最後のフリマ、寂しいですね」
「でも、また来年もやるんでしょう?」
「そうだといいんですけど……」
みずなは、来年もゆうなと一緒に運営できるのか、不安だった。もしかしたら、これで最後かもしれない。そう思うと、胸が締め付けられた。
午後1時。
突然、空が暗くなった。
「あれ……?」
みずなが空を見上げる。厚い雲が、空を覆っている。
そして——
ひらり
白いものが、一つ落ちてきた。
「雪……?」
ゆうなも空を見上げる。
次の瞬間、雪が本格的に降り始めた。
「え……予報では雪なんて言ってなかったのに……」
みずなが慌てる。来場者たちも、突然の雪に驚いている。
最初は、雪を楽しむ雰囲気もあった。子供たちが喜んで手を広げている。
しかし、雪はどんどん激しくなっていった。
「これは……まずいな」ゆうなが表情を曇らせる。
気温も急激に下がってきた。来場者たちは、寒さに耐えかねて帰り始める。出店者たちも、商品が濡れないようにシートをかけ始めた。
「このままじゃ、最後が寂しい終わり方になっちゃう……」
みずなが悲しそうに呟く。
せっかくの最終日なのに。みんなで楽しく終わりたかったのに。
その時、ゆうなが何かを思いついた顔をした。
「みずな」
「はい?」
「何か温かいものを配りたいな」
「温かいもの……?」
「はい。こんな寒い日に、温かい飲み物があれば、みんな少しは元気になるかもしれません」
ゆうなの目が、真剣だった。
「でも、どこで……」
「近くにドンキホーテがありますよね。そこで買ってこよう」
「そんな……ゆうなさん、寒いですよ……」
「大丈夫です」ゆうなが微笑む。「みずな、一緒に来てくれる?」
みずなは、少しだけ躊躇した。でも、ゆうなの真剣な目を見て、決心した。
「はい。一緒に行きます」
二人は、雪の中を走り始めた。
ドンキホーテへの道
公園から徒歩10分のドンキホーテ。しかし、雪の中を走るのは思ったより大変だった。
「みずな、大丈夫?」
「うん、大丈夫」
みずなは、息を切らしながら答える。寒い。手がかじかんで、感覚がなくなってきた。
でも、ゆうなと一緒なら、頑張れる。
ドンキホーテに着くと、二人は飲料コーナーへ直行した。
「温かい飲み物……ココアは?」みずなが提案する。
「いいですね。でも……」ゆうなが商品棚を見渡す。「ゆず茶もあるじゃん」
「ゆず茶って?」
「そそ。韓国のゆず茶ね。お湯で溶かすタイプの」
ゆうなが手に取ったのは、大きな瓶に入ったゆず茶。
「これ、体が温まるし。それに、ビタミンCも豊富で。おれが好きなんだけどね」
「そそ、いつも買ってくるからね。じゃあ、これにしよう」
みずなも頷く。
二人は、大量のゆず茶を購入した。10瓶以上。レジの店員さんも驚いていた。
「重いかも……」みずなが袋を持ち上げる。
「二人で分けようか」
ゆうなが半分以上を持つ。
そして、二人は再び雪の中を走った。
行きよりも、帰りの方が大変だった。重い荷物を持って、雪の中を走る。息が白い。手は凍えている。でも、不思議と楽しかった。
「みずな、もう少しだよ」
「はい」
二人は並んで走る。時々、足を滑らせそうになるが、お互いに支え合う。
「ゆうなさん」
「はい?」
「私……ゆうなさんと一緒で良かったです」
みずなが、息を切らしながら言う。
「この半年間、本当に楽しかったです。ゆうなさんがいなかったら、絶対に続けられませんでした」
ゆうなは、少し驚いた顔をした。そして、優しく微笑んだ。
「おれもだよ。みずなと一緒だったから、楽しかったし」
二人は、顔を見合わせて笑った。
そして、公園に戻った。
温かいゆず茶
「お待たせしました!」
二人が戻ってくると、出店者たちが驚いた顔をした。
「お二人、どこに行ってたんですか?」
「ずぶ濡れじゃないですか」
ゆうなとみずなは、確かにずぶ濡れだった。雪で服も髪も濡れている。でも、二人とも笑顔だった。
「温かいゆず茶を買ってきました」ゆうなが袋を掲げる。「みんなで飲みましょう」
出店者たちは、一瞬戸惑った。でも、すぐに嬉しそうな顔をした。
「ありがとうございます!」
「これは嬉しい!」
みずなは、急いでお湯を沸かした。受付テントにある電気ポットで、大量のお湯を作る。
そして、紙コップにゆず茶を入れて、お湯を注ぐ。甘い香りが、会場中に広がった。
「はい、どうぞ」
みずなとゆうなは、出店者と来場者に温かいゆず茶を配って回った。
「温かい……」
「ありがとう」
「体が温まるね」
みんなの顔が、少しずつ笑顔になっていく。
哲学者風のおじさんも、元カレグッズのおばさんも、骨董品のおじいさんも、手作り雑貨のおばあさんも、ポーランド人の青年も。
みんな、温かいゆず茶を飲んで、笑顔になった。
「お二人のおかげで、最高の最終日になりましたよ」
骨董品のおじいさんが、嬉しそうに言う。
「いえ、みんなのおかげです」ゆうなが微笑む。
会場は、再び温かい空気に包まれた。雪は降り続けているが、もう寒さを感じない。
みずなは、その光景を見て、胸がいっぱいになった。
(ゆうなさんのおかげだ)
ゆうなの優しさが、みんなを笑顔にした。
(やっぱり、すごい人だな)
第六章:夕暮れの告白
午後5時。
フリーマーケットが終了し、出店者たちが帰っていく。
「お疲れ様でした!」
「また来年も!」
「お二人も、お体に気をつけて!」
温かい言葉をもらいながら、みんなが帰っていった。
そして、会場には二人だけが残った。
「片付けましょうか」
「はい」
二人は、テントを畳み、テーブルを片付け、ゴミを集める。いつもの作業。でも、今日で最後。
雪はやんでいた。空は晴れ、夕焼けが差し込んでいる。オレンジ色の光が、白い雪を照らして、幻想的な景色を作り出していた。
片付けが終わり、二人はベンチに座った。
疲れ果てていた。でも、心地よい疲れだった。
「お疲れ様でした」ゆうなが言う。
「お疲れ様でした」みずなも答える。
二人とも、まだ少し濡れていた服を着ている。寒いはずなのに、不思議と寒くない。
ゆうなが、残っていたゆず茶を取り出した。
「最後に、二人で飲もうっか」
「はい」
ゆうなが、紙コップに二つ、ゆず茶を作る。お湯を注ぐと、甘い香りが再び広がった。
二人は、冷え切った手でカップを持った。温かい。
「……美味しいですね」みずなが小さく言う。
「うん、温まるよね」
二人は、静かにゆず茶を飲む。
夕焼けが、少しずつ暗くなっていく。空がオレンジから紫へと変わっていく。
「みずな」
ゆうなが、静かに口を開いた。
「はい」
「この半年間、本当にありがとう」
「いえ、こちらこそ……」
「みずなと一緒に運営できて、本当に楽しかったよ」
ゆうなの声は、いつもより少し優しい。
「色々なトラブルがあったけど、みずながいてくれたから、乗り越えられました」
「そんな……私なんて、失敗ばかりで……」
「そんなことないよ」ゆうなが真剣な顔で言う。「みずなは、いつも一生懸命で、優しくて、素敵な人だよ」
みずなは、顔が熱くなるのを感じた。
「ゆうなさん……」
「あの……これからも、一緒に何かやりませんか?」
ゆうなが、少し躊躇してから続ける。
「フリマは終わっちゃいますけど、また別の活動でも……」
みずなの心臓が、激しく鳴った。
これは、どういう意味だろう。ただの友達として、一緒にいたいということ?それとも……
「私も……」
みずなが、勇気を出して言う。
「私も、ゆうなさんと……ずっと一緒にいたいです」
ゆうなが、驚いた顔をした。
「この半年間、ゆうなさんと過ごせて、本当に幸せでした」
みずなの声は、少し震えていた。でも、言わなきゃいけない。今言わないと、後悔する。
「ゆうなさんは、いつも冷静で、優しくて、かっこよくて……最初は、尊敬してただけだったんです。でも、いつの間にか……」
みずなは、一度言葉を切った。そして、勇気を振り絞って続けた。
「好きになってました」
静寂。
ゆうなは、しばらく何も言わなかった。
みずなは、心臓が止まりそうだった。言っちゃった。本当に、言っちゃった。
でも、後悔はなかった。
「……僕も」
ゆうなが、静かに言った。
「え?」
「僕も、みずなのことが好きだよ」
みずなは、耳を疑った。
「本当……ですか?」
「はい」ゆうなが微笑む。「最初は、一緒に仕事をする仲間として見てましたけど、いつの間にか……みずなの笑顔が見たくて、会いたくて、ずっと一緒にいたいって思うようになってました」
みずなの目から、涙が溢れた。
「良かった……」
嬉しくて、嬉しくて、涙が止まらない。
「ちょっとちょっと……泣かないでって」ゆうなが慌てる。「僕、何か変なこと言っちゃった?」
「違うって」みずなが笑いながら涙を拭く。「嬉しくて……嬉しすぎて……」
ゆうなも、安心したように笑った。
二人は、しばらく無言で座っていた。
そして、ゆうなが静かに手を伸ばした。
みずなの手に、そっと触れる。
「……いいですか?」
みずなは、頷いた。
ゆうなの手が、みずなの手を包み込む。
温かかった。
ゆず茶よりも、ずっと温かかった。
「ゆうなさんの手……温かいです」
「みずなの手も、温かいよ」
二人は、顔を見合わせて笑った。
空がすっかり暗くなり、星が見え始めた。雪に反射して、星がキラキラと輝いている。
「寒くない?」ゆうなが心配そうに聞く。
「はい、全然寒くないです」
みずなは、本当にそう思っていた。
ゆうなと手を繋いでいるだけで、体中が温かい。
「これから……」ゆうなが静かに言う。「これからも、ずっと一緒にいてくれる?」
「もちろん」みずなが即答する。「ずっと、一緒にいよう」
二人の手が、ぎゅっと握り合った。
雪の降った日の夕暮れ。
ドンキホーテで買ったゆず茶。
そして、二人だけの特別な時間。
エピローグ:春、新しい始まり
それから三ヶ月後。
春の訪れとともに、公園の桜が満開になった。
「みずな、こっちこっち」
ゆうなが手を振っている。その隣には、見慣れた受付テント。
そう、今日は新しいフリーマーケットの初日だった。
「お待たせしました」
みずなが駆け寄ると、ゆうなが自然に手を繋いできた。
「遅刻しないで来られたね」
「寝起きよくないのにゆうなさんがちゃんと起こしてくれたから。」
「みずなを起こしてあげられるの、僕だけじゃない」
「確かにね。」
二人は笑いながら、受付テントの準備を始める。テーブルを並べ、椅子を置き、看板を立てる。もう、完璧な連携だった。
「あ、お二人さん!」
声をかけてきたのは、哲学者風のおじさんだった。
「今年もよろしくね」
「こちらこそ」
次々と、去年の出店者たちがやってくる。元カレグッズのおばさん(今年は「新しい彼氏からもらったプレゼント」を販売するらしい)、骨董品のおじいさん、手作り雑貨のおばあさん、ポーランド人の青年……
みんな、去年と変わらない笑顔だった。
「お二人、付き合ってるんでしょ?」元カレグッズのおばさんがニヤリと笑う。
「え?わかります?」みずなが恥ずかしながら、素早く返した。
「やっぱりね!去年から分かってたわよ。恋愛経験豊富なお姉さんは何でも分かるんだから。フラれた経験もあるけど・・・・」
おばさん、いやお姉さんが笑う。
「仲良くしていくんだよ」
「ありがとうございます」
午前9時。
「では、開会します!」
ゆうなの掛け声で、新しいフリーマーケットが始まった。
春の陽気に誘われて、たくさんの来場者が集まってくる。子供たちが走り回り、家族連れが笑顔で商品を見ている。
みずなは、その光景を見て微笑んだ。
一年前、ここで出会った。
予想外のトラブルだらけで、大変だったけど、楽しかった。
「みずな」
「はい?」
「今日の帰り、ドンキ寄ってかない?」
「ドンキ?」
「うん。ゆず茶、買っておきたいなって。あ、お菓子コーナーも見たいな」
ゆうなが笑う。
「次の冬に備えて」
みずなも笑った。
「うん、一緒に行こう」
二人は、手を繋いだまま、来場者を迎え入れる。
春の風が、優しく吹いている。
桜の花びらが、ひらひらと舞っている。
そして、二人の未来は、これからも続いていく。
雪の日に温めたゆず茶のように、ずっと温かく。
【完】
あとがき
フリーマーケットは、不用品に新しい命を吹き込む場所。
でも、それだけじゃない。
人と人が出会い、つながり、温かい時間を共有する場所。
予想外のトラブル、困難な状況、寒い冬の日。
でも、二人で協力すれば、何でも乗り越えられた。
大切なのは、一緒にいる人。
そして、その人と分かち合う、温かい時間。
ドンキホーテで買ったゆず茶が、二人を繋いだ。
これからも、二人はずっと一緒に、色々なことに挑戦していくだろう。
フリーマーケットも、その他の活動も。
そして、いつか――
二人は、これからも毎週この公園で、笑顔で会い続けるだろう。
出店者たちと語り合い、来場者を迎え入れ、温かい時間を共有する。
春には桜の下で、夏には木陰で、秋には紅葉を眺めながら、冬には温かいゆず茶を飲みながら。
「来週も、一緒に」
「はい、ずっと一緒に」
そんな日々が、これからもずっと続いていく。
変わらない気持ちで、ずっと好きでいられるように。
Special Thanks
- すべての出店者の皆様
- フリーマーケットという素敵な場所
- ドンキホーテのゆず茶
- そして、雪の日に勇気を出して気持ちを伝えたすべての人たちへ
「好き」は、素直に伝えよう。そして、温かいゆず茶を一緒に飲もう。